2022.01.08|その他
中山間農業が輝くためにできること
うちが所有している畑には、元々原野だったりして農地では無かった土地を、戦後、国が事業として開発し、農地に造成されたものが多くあります。
農地の造成と併せて灌漑設備も整備されたので、農業にとって最も大事なものの1つである水が、高台にある畑にも届くようになりました。
米作中心だった我が地域は、比較的大規模な畑と農業用水が与えられたことで、その後の農業経営の多角化が可能になりました。
ただ、大規模といっても、それはあくまで”中山間地としては”という話。
元々原野や森林だった土地なので傾斜地も多いし、一体的に利用できる農地は限られています。
それに、畑の形状も、きれいな四角形ではない不整形な畑が多い。
一部のほ場をドローンで空撮してみましたが、上から見ても形が良くないですよね(;^_^A
日本の中山間地農業が規模拡大して効率化できない所以です。
限られた農地をいかにして効率よく利用できるか、頭を使って考えるわけですが、それも限界があります。
耕地利用率を限界まで高めて、栽培技術を高めつつ収量を増やして、作業工程を見直して労働生産性を高めて・・・
それでも太刀打ちできないのであれば、中山間地農業は廃れていくしかないのか?
いや、そんなことはありません。
平野部のように広大な農地は無くても、効率化は簡単に進められなくても、中山間地にもメリットがあるし、本当はできることがたくさんあります。
これまでのやり方を変えようとせずに、農業の行く末を嘆いてみせる。
そんな農家ばかりでは、現状は1ミリも良くなりません。
前世代が培った経験や知恵を継承しつつ、自由な発想で時代の変化に対応できるかどうか。
かつて何も無かった土地を開いて農地が生まれたように、硬直化した農業界を開拓していくチャレンジ精神を忘れないようにしたいと思います。
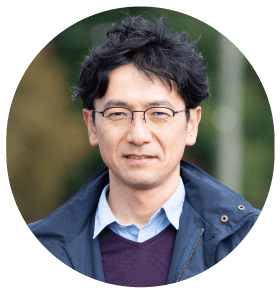
梶原耕藝 代表梶原甲亮(かじわらこうすけ)
1976年生まれ(43歳)。熊本県山都町在住。代々続く農家の7代目。九州大学法学部政治学科を卒業して熊本県庁に就職。子供が生まれ、食への関心が高まると共に「安心安全な食べ物を届けたい」「農業を夢のある仕事にしたい」という想いでUターン。現在、3兄弟の父親として日々学びながら農業を取り組んでいます!
最新記事
KEYWORDS
- AGRI PICK
- GoPro
- Kindle
- Metagri研究所
- NFT
- Uターン
- vlog
- webマーケティング
- YouTube
- オーガニック
- カメラ
- くまもと農業経営塾
- クラウドファンディング
- クロマルハナバチ
- こだわり
- コミュニティ
- ストレス栽培
- タバコカスミカメ
- トマト
- トマトの歴史
- トマトの準備
- トマトの育て方
- ドローン
- ニンジン
- ニンニク
- パッケージ
- フルティカ
- ブログ
- ブロックチェーン
- ほれまる
- まちづくり
- ミツバチ
- メタバース
- メルマガ
- ロゴ
- 中山間地
- 価値
- 優里の会
- 元公務員
- 共同作業
- 写真
- 加工品
- 加工品開発
- 労働環境
- 子ども
- 子育て
- 寄付
- 屋号
- 山都町
- 微生物
- 新規就農
- 日の宮
- 映像制作
- 暑さ対策
- 有機
- 有機JAS
- 有機栽培
- 有機農業
- 本
- 梶原家の歴史
- 歴史
- 生理障害
- 田植え
- 病害虫
- 直接販売
- 移住
- 米
- 結び方
- 耕藝
- 自然災害
- 落花生
- 親元就農
- 転職
- 農家の嫁
- 農業vlog
- 農業コンクール
- 農業で稼ぐ
- 農業の誇り
- 農業ビジネススクール
- 農業マーケティング
- 里親制度
- 障害
- 雪
- 高温対策
- 高糖度トマト
- 鳥獣害




