2020.05.13|農家の日常
新しい従業員がやってきた
畑に新しい従業員がやってきました!
これからのシーズン、とても頼りがいのあるヤツらです。
名前を「クロマルハナバチ」といいます。
トマトの花粉を媒介してもらうために畑に入れました。

これが巣箱です。
箱の中には女王バチがいて、子を産みつづけます。
一般的に、トマトの花粉媒介にはヨーロッパ原産の「セイヨウマルハナバチ」が使われています。
ただし、外来種のハチなのでハウス外に逃げ出してしまうと、地域の生態系を乱してしまう懸念があります。
一方、クロマルハナバチは在来種で山都町にも生息しています。
うちの家の裏にあるシャクナゲの花には、野生のクロマルハナバチが何匹もやってきます。
ただし、在来種とはいえハウス外に出さないように、全ハウスの換気部分をネットで覆うなどの対策をします。
クロマルハナバチは紫外線カットのハウスフィルムではあまり働かないとされているんですよね。
それが、セイヨウマルハナバチの方が農業用に用いられている理由です。
私は可能なかぎり在来のハチを使いたかったので、周りには使っている人はほとんどいない中でクロにしました。
うちも紫外線カットフィルムを使っていて、クロマルハナバチを入れる前はちょっと心配しましたが、結果、何の問題もなく働いてくれています。
聞いた話を鵜呑みにすることなく、何でも自分で試してみることが大事ですね!

それと、マルハナバチがちゃんと受粉させてくれているか、確認する方法があります。
トマトの花の雄しべを見ると、茶色い跡が残っていることがあります(上の写真)。
これを「バイトマーク」といって、マルハナバチが花粉を集めるときに雄しべに噛みついた跡です。
「bite(噛む)mark」ってことですね(^^)
自分たちが見ていないところで彼らが働いてくれるからこそ、花が実になり、トマトとして収穫できるようになるんですよね。
ありがたい存在です。
それでは、彼らの働きに負けないように自分もがんばりたいと思います!
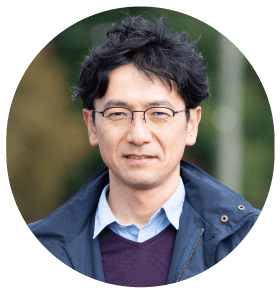
梶原耕藝 代表梶原甲亮(かじわらこうすけ)
1976年生まれ(43歳)。熊本県山都町在住。代々続く農家の7代目。九州大学法学部政治学科を卒業して熊本県庁に就職。子供が生まれ、食への関心が高まると共に「安心安全な食べ物を届けたい」「農業を夢のある仕事にしたい」という想いでUターン。現在、3兄弟の父親として日々学びながら農業を取り組んでいます!
最新記事
KEYWORDS
- AGRI PICK
- GoPro
- Kindle
- Metagri研究所
- NFT
- Uターン
- vlog
- webマーケティング
- YouTube
- オーガニック
- カメラ
- くまもと農業経営塾
- クラウドファンディング
- クロマルハナバチ
- こだわり
- コミュニティ
- ストレス栽培
- タバコカスミカメ
- トマト
- トマトの歴史
- トマトの準備
- トマトの育て方
- ドローン
- ニンジン
- ニンニク
- パッケージ
- ふるさと納税
- フルティカ
- ブログ
- ブロックチェーン
- ほれまる
- まちづくり
- ミツバチ
- メタバース
- メルマガ
- ロゴ
- 中山間地
- 価値
- 優里の会
- 元公務員
- 共同作業
- 写真
- 加工品
- 加工品開発
- 労働環境
- 子ども
- 子育て
- 寄付
- 屋号
- 山都町
- 微生物
- 新規就農
- 日の宮
- 映像制作
- 暑さ対策
- 有機
- 有機JAS
- 有機栽培
- 有機農業
- 本
- 梶原家の歴史
- 歴史
- 生成AI
- 生理障害
- 田植え
- 病害虫
- 直接販売
- 移住
- 米
- 結び方
- 耕藝
- 自然災害
- 落花生
- 親元就農
- 転職
- 農家の嫁
- 農業vlog
- 農業コンクール
- 農業で稼ぐ
- 農業の誇り
- 農業ビジネススクール
- 農業マーケティング
- 里親制度
- 障害
- 雪
- 高温対策
- 高糖度トマト
- 鳥獣害




