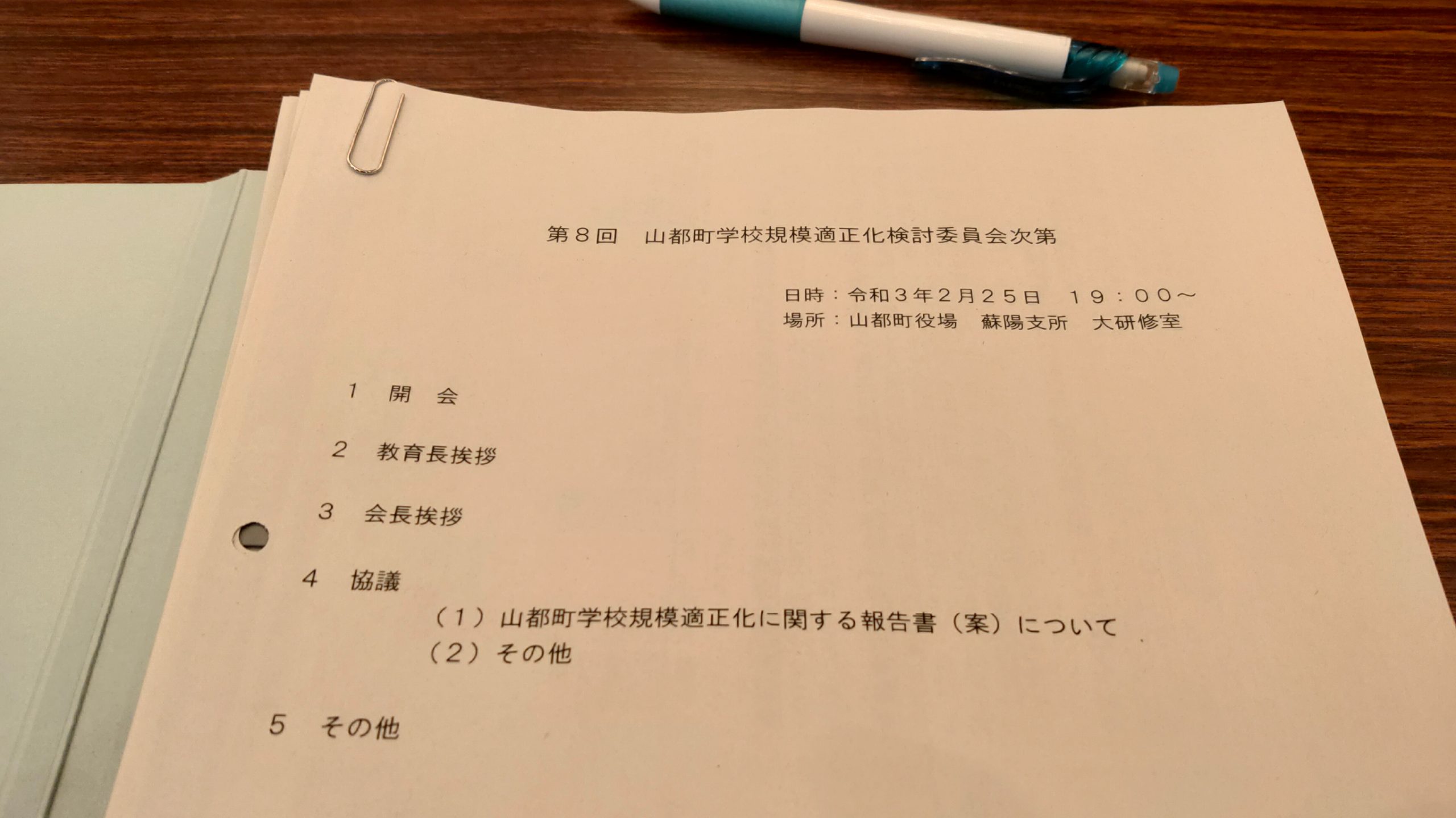2021.02.26|その他
山都の学校のミライ
昨夜、山都町教育委員会主催の会議に参加しました。
「山都町学校規模適正化検討委員会」
早い話、町内小中学校の規模・配置に関して、統廃合も含めた方策を検討する会議です。
私は、地元小学校のPTA会長をしていて、学校の代表として1年以上前から会議に参加してきました。
昨夜が委員会の最終日。
この委員会で報告書をとりまとめて、来年度以降の教育委員会での方針づくりに活かされます。
自分は、会議に参加したら何かしら発言することをテーマにしているので、毎回意見を述べさせてもらいました。
山都町の子どもの人口推計を見ると、今後どんどん児童数が減っていく。
減ることは致し方ないにしても、だからといって「統廃合はやむを得ない」という思考に落ち着くのは違和感を持っていました。
「小規模校では社会性が育たない」
よく言われることですが、複式学級出身の自分からすると、カチンとくることもあります(;’∀’)
「クラス替えできる程度の学校規模が望ましい」というのが、文部科学省の示す基準です。
たしかに、一定規模の子どもがいることが、子どもにとって良い影響を与えることもあります。
部活動だって選択肢が多いし、いろんな学校行事もやりやすい。
子どもも大人も寂しい思いをしなくて済む。
ただ、これまでの学校という枠組み、システムじたいが、時代に合わせて変わっていくのではないか。
学校現場には今後ICTの導入が進んで、外部といつでもつながることができる。
学校だけが学びの場では無くなっていくでしょう。
現に、うちの長男はYouTubeで配信されてる動画を観て、予習をしたり、学校では学べないことを学んでいます。
子どもだけでなく、大人にとっても、学校が学びの場になる。
そういう玉石混交の場であって良い。
むしろ、小規模校の”小回りが利く”というメリットを活かして、地域に溶け込んでいけば良い。
時代が大きく移り変わり、社会が学校に求めていることが変化してきているけど、学校の配置や規模に関する議論が、どうしても既存の枠組みのなかに留まってしまうのは残念だな~
・・・というのが、率直な感想でした。
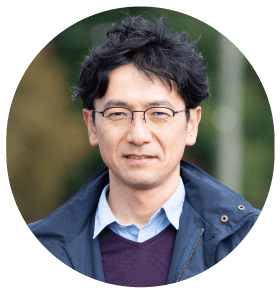
梶原耕藝 代表梶原甲亮(かじわらこうすけ)
1976年生まれ(43歳)。熊本県山都町在住。代々続く農家の7代目。九州大学法学部政治学科を卒業して熊本県庁に就職。子供が生まれ、食への関心が高まると共に「安心安全な食べ物を届けたい」「農業を夢のある仕事にしたい」という想いでUターン。現在、3兄弟の父親として日々学びながら農業を取り組んでいます!
最新記事
KEYWORDS
- AGRI PICK
- GoPro
- GREEN TIDE
- Kindle
- Metagri研究所
- NFT
- Uターン
- vlog
- webマーケティング
- YouTube
- オーガニック
- カメラ
- くまもと農業経営塾
- クラウドファンディング
- クロマルハナバチ
- こだわり
- コミュニティ
- ストレス栽培
- タバコカスミカメ
- トマト
- トマトジュース
- トマトの歴史
- トマトの準備
- トマトの育て方
- ドローン
- ニンジン
- ニンニク
- パッケージ
- ふるさと納税
- フルティカ
- ブログ
- ブロックチェーン
- ほれまる
- まちづくり
- ミツバチ
- メタバース
- メルマガ
- ロゴ
- 中山間地
- 価値
- 優里の会
- 元公務員
- 共同作業
- 写真
- 加工品
- 加工品開発
- 労働環境
- 子ども
- 子育て
- 寄付
- 屋号
- 山都町
- 微生物
- 新規就農
- 日の宮
- 映像制作
- 暑さ対策
- 有機
- 有機JAS
- 有機栽培
- 有機農業
- 本
- 梶原家の歴史
- 歴史
- 生成AI
- 生理障害
- 田植え
- 病害虫
- 百年
- 直接販売
- 移住
- 米
- 結び方
- 耕藝
- 自然災害
- 落花生
- 親元就農
- 転職
- 農家の嫁
- 農業vlog
- 農業コンクール
- 農業で稼ぐ
- 農業の誇り
- 農業ビジネススクール
- 農業マーケティング
- 里親制度
- 障害
- 雪
- 高温対策
- 高糖度トマト
- 鳥獣害